 Episode XI : 夏祭り
Episode XI : 夏祭りEpisode XI : 夏祭り
|
古くさいと言われるかも知れないが、あたしは夏の初めからお盆の時期の年中行事を忘れない。 と言っても、このあたりの伝統行事をそのまま記憶している人は少なくて、どちらかというとみんなの心の中にある夏の行事のイメージを元に、それらしいことをしているだけだ。そもそもそれ以前の問題として、神戸には本当に古くからの人はほとんどいない。まだ華やかだったころには、神戸は大阪まで続いた「都市圏」の一部だったし、こと、旧神戸市地域の東側は大阪のベットタウンと言っても過言ではない。世の中が静かになっても、神戸には、水没した大阪市や、廃村となった「ひょうごの国」北部から引っ越してきた人が多くなっている。みんなの「年中行事」の記憶も思い思いだし、都会暮らしの長い人になると、そもそも古くからのしきたりを知らない人も少なくない。 そんな事情だから、なにをもって「正しい」伝統行事なのか、と聞かれると、誰にも答えられない。 もっとも、どの国に行ってもこの事情は同じ。ある意味「みやこ」の人が特殊だと言っていい。 しかしその中で、誰もが共通に思いつく行事が夏祭りだったのは、ある意味で当然だろう。結果として神戸にも、夏の前半のある日に、盛大に夏祭りをする習慣が出来てしまった。伝統行事としてはけして正しくはないのだろうが、まぁ別に、ちょっとくらい間違っていても、みんなが楽しんでいるのだから構わないと思う。 ここ数年ほど、夏祭りはいつもアキオと過ごしている。その前までは夏祭りは先生と一緒だった……どちらかというとはしゃいでいたのはあたし一人だったが。だから、夏祭りの日はひとりでのんびりしたい気持ちもあるが、さりとて、アキオの思いを無視するわけにもいかず、あたしは夏祭りの日に関しては、いつも妥協することにしていた。 そのかわり、ささやかな抵抗として、迎え火の日はいつも一人で出かけている。もちろん、アキオには秘密だ。もっとも彼は、もう気づいているようだが……。 まぁ迎え火はともかく(実際、この行事をきちんとしている人は少ないのだが)、夏祭りに関しては、六甲の人たちはもうひと月も前から準備をしている様子だった。祭りも以前はちょっと提灯が出て神事っぽいことをやっていた程度だったが、ここ何年かはだんだんと賑やかになってきている。もちろん、昔と比べればそれでもこぢんまりしているが、それでもその雰囲気を思い出すだけで心が躍ってくる。 例によってあたしは、その日になると、例年のように店の入り口の札を「Closed」にする。出かけるのは昼を過ぎたころだ。去年「みやこ」で買った浴衣を着て、さぁ出かけよう、と嬉々としていると、予測していたように、ちょうどアキオがやってくる。 「なんや、またその格好か」 彼は、まだ遊び盛りの二匹の仔猫をいじくりつつ、あたしの浴衣姿に失礼なことを言いってニヤニヤしている。あたしはちょっと恥ずかしくなって、頬を膨らませながらアキオの背中を一つ叩こうとするが、彼はひょい、と避けてしまい、あたしは空振りしてしまった。 「いいじゃない、夏祭りなんだから」 「みかげ、前から言おう思うとったんやけどな」 「なに?」 「ぜんぜん似合うとらんで」 「もぅっ!」 ちょっとムキになってアキオを追いかけ回してしまう。しばし、店の前を二人で走り回っていると、すぐ下の家の人が、畑仕事の手を止めて笑いながら見ているのに気づいてしまった。あたしたちはつい、顔を赤らめてその場に立ち止まった。 「これから夏祭り?」 「うん、アキオとバイクで行くとこ」 「その浴衣、ええよ、いかにも夏祭りらしいわ」 「そ、そうだよね」 下の人の言葉に、あたしは勝ち誇ったような顔でアキオを見る。アキオのほうは、その会話がさも気に入らない、というように、わざとらしく口をとがらせて横を向いてしまった。 じゃれあいもそこそこに、ベータに留守番をさせて、それぞれのバイクで出発。いつものコースで街に出た。バイクを停めて歩き始めた街並みはもう、屋台の列。そのにぎわいは下京のそれには遠く及ばないものの、まだ明るいうちからたくさん出ていて、普段は商店街から外れているために人通りもまばらな道は、今日は大混雑だ。 「やっぱ、綿菓子やろ」 アキオが言う。毎年の恒例行事になっているが、もちろんあたしも全く文句はない。二人で頭よりも大きいジャンボサイズの綿菓子を買って通りを歩く。どちらとも口の周りは砂糖だらけ、それから、その砂糖を周りの人につけないようにするのに、ちょっと苦労する。 ついでに、真っ赤なアンズ飴も。屋台の定番だ。 「みやこの屋台もいいけど、やっぱりこっちもいいよね」 「せやけど、やっぱ葛切りは欲しいなぁ」 「あ、それ言えてる。ここの祭りにも来ないかな」 まったくもって無責任な会話。そうしてあたしたちは雑然とした空気を楽しんでいる。何度かアキオとはぐれそうになるが、慌ててお互いを探すのが、また楽しかったりする。こと、背の低いアキオは人混みに紛れるとどこに行ったのか全くわからない。あたしの赤みの強い髪だけが目印だ。 色とりどりの屋台が、そろそろ薄暗くなり始めた坂道を飾っている。たこ焼きやらかき氷やら、いかにもお祭りらしい食べ物の屋台の間に、当たりクジやら、いかにも子供だましな小物を無数にぶらさげた小物屋やらがある。例によって射的の屋台が今年も出ていて、あたしたちはつい挑戦してしまう。 「あ〜、当たっとうのに、なんで落ちへんの」 「こういうのはさぁ、弾をめいっぱい詰め込んで、こうやってさぁ」 やや怒り顔のアキオの前で、あたしは「鉄砲」を持った右手を伸ばして、台から思いっきり身を乗り出す。とにかく近づけるしかないのだ……。 「上の方を狙わないと落ちないよ。ほら」 言いながら撃つが、なんだか楽しそうなデザインのネズミの人形に、コルクの弾がしっかりと当たっているのにやっぱり落ちない。店の兄さんが、さもおかしそうに笑っているのを見て、あたしはカチン、と来た。 「これ、絶対おかしいっ!」 「みかげが下手くそなだけちゃうか」 「い〜や、絶対おかしい」 あたしは頬を膨らませ、ムキになって同じ景品を狙って何度か挑戦したが、やっぱりうまく行かない。ようやく落ちたころにはかなりの時間とお金を費やしていた。アキオのほうが、やれやれ、といった感じで苦笑い。なんとなく立場が逆転している。 「も、ええか?」 「やっぱりあれ、おかしいよ〜。あんだけやっても落ちないんだから〜」 ぶつぶつ文句を言うが、やっぱり来年になると挑戦してしまうんだろうと、自分でも感じている。 まぁ、景品はとれたんだから、いいとするか。 ネズミの人形をぶらぶらさせてまた歩き出しす。そうやって何件かの夜店をひやかしているうちにあたしは、坂の上の方で思わぬものを見つけた 「あ、型抜きだ!」 あたしはつい声を上げてしまう。人混みをわけて駆け寄るあたしに、アキオが慌ててついてくるが、その屋台の前に置かれた即席の低い机と、上に散乱する色とりどりの破片を見て、戸惑った表情だった。 「な、なんや、これ」 「型抜き、知らないの? うわ、これ、どこから見つけてきたんだろ、懐かし〜」 既に何人かの親子連れが、一心不乱に挑戦している。どっちかというと熱心なのはお父さんのほう、という感じもするが。 知らない人がいるといけないので念のために説明しておくが、型抜きというのは、たぶん砂糖か何かを固めたものだと思うのだが、独特の材質の板に、複雑な形(普通は動物や車などの形をしている)の溝が掘ってあって、その溝の外側だけを、針を使って全て切り出せば景品が……昔はお金だったこともあるようだが……もらえる、という遊びだ。 もちろん、お祭りの屋台限定。 「おじさ〜ん、このゾウの形の、ちょうだい」 「あいよ」 ひげ面の、なんだか無愛想な親父が、無造作に紙に包まれた小さな板を放ってよこす。あたしは代金を支払い、机(というか、ただの木の板)の片隅で挑戦した。 「なんや、いちばん簡単なヤツやんか」 「まぁね〜。アキオもやる?」 「ほなおっちゃん、オレはこの傘の形の、いくわ」 アキオは、かなり上級編を選んでいる。開いた傘の形の柄のあたりが、みるからに細くて簡単に壊れそうだ。 「見てるより難しいよ」 「平気やて。ほれ」 無造作にはじっこから始めている。あたしは、大きなところを大まかに落とすと、慎重に切り崩しているが、それでも冷や汗ものなのだ。予想通りアキオは1分も立たないうちに、細い部分どころか傘全体ををまっぷたつにしてしまった。 「わ、急にわれよった」 「だから難しいっんだって。割れたらこれ、食べられるんだよね。あんまりおいしくないけど」 アキオは少し悔しそうな顔で、大きい方のかけらを口に入れ、あたしの手元を見た。ほとんど進んでいないのを見て、また少し憮然とした表情になる。 「おっちゃん、今度はこっちでええわ」 「おう」 アキオがまた別なのに挑戦している間に、あたしは少しずつ進める。考えてみたらバカみたいな遊びだが、なんだか夢中になるというか、ムキになってしまう。アキオはまた、無造作な作業で細いところを割ってしまって、むこうで爆発している。あたしはあと少しというところまでいったが、惜しいところで、やっぱりゾウの鼻の付け根の部分を割ってしまった。 「あ〜、悔しい〜」 「なんや、オレもうええわ」 言うことはこんな感じだが、表情はなんだか笑い顔。あたしたちは、こわばった膝を伸ばしながらよろよろと立ち上がって、服についた板のかけらを払い落とす。 あたしの右手はもう、すっかりかたくなって、大きく振ってほぐしてやらなければならない。横でアキオはノビをした。 ちょっと子供心に帰った感じ。こういうのも、祭りに来た人の特権なんだろう。 型抜きの屋台を後に、そのままいくつもの屋台をまわり、あたしたちは相変わらず食べ物ばかり買いあさっている。途中、小さな神輿を担いだ人の列が坂の上から下りてきて、あたしたちは道の左右にわかれた人の群れの中でそれを見ている。ものすごい熱気に、あたしはつい興奮して、周囲の人と一緒にかけ声をかけている。 「ほんま、すごいわぁ」 列が通り過ぎたあと、アキオがそうもらした。その感想はあたしも全く同じだったから、うん、とだけ答えてしまう。 「どこから出して来たのかなぁ。やっぱりみんな、こういうの好きなんだよね」 「ほんま、お祭り、って雰囲気やな」 「来年はアキオも挑戦してみたら?」 「お、ええな」 その人の列も、坂の下に消えていってしまう。あたりには、どこか興奮したような空気だけが漂っていた。 と、不意にあたしを、聞き覚えのある声が呼び止めた。 「あら、みかげ、来てたの?」 驚いて振り返ると、ハルナだった。あの病院の大池先生の娘さんだ。 「わ、ハルナじゃない。帰ってくるのあさってじゃなかったの?」 「それが、急に今日の朝に帰れることになったのよ。いま、お父さんの仕事を手伝ってるところ」 「そうなんだ。どうだった、「みやこ」の留学は」 「なんとか、ね。あんまり本ばっかり呼んでるわけにもいかないし、こっちで実地の勉強もしなきゃ」 「そっかぁ。また神戸にお医者さんが一人増えるね」 「そんな、わたしはまだまよ。お父さんから色々勉強しないと。ほんとに見習い、って感じ」 つい会話が弾む。彼女とはここ何年かのうちに二、三度しか会っていないだけなのに、そんなことはほとんど感じない。少しお喋りしながら、ふとアキオを見ると、あたしの横でなんだかソワソワしているだけで、一向に会話には入ってこない。あたしは、おや、と思う。彼だって、ハルナはもう何年も前から知っているはずだから、人見知りするような相手ではないのだが……。 「そうそう、みかげ、今夜の花火行く?」 「行く行く」 ちょっと気がそれていたあたしは、ハルナが不意に言われ、思わず表情を明るくして大きく首を縦に振った。そう、今夜はかつてのポートアイランドのあたりから花火が上がることになっているのだ。 そのために神戸の人たちはもう、数週間も前から浮かれ通しだったりする。もちろん、仕事も手につかない子供たちが(中には大人たちも)多々。みんな、花火の話を始めると止まらない状態だ。あたしだってその気分は変わらないし、行くかどうかなんて、聞くまでもないことだ。 「花火なんて「いばらきの国」で見て以来なんだよね。楽しみだな〜」 「わたしも「みやこ」で二回見ただけだし。そうだ、アキオ君は花火、初めてじゃない?」 「へ?」 不意にハルナに話を振られ、アキオは食べかけのイカ焼き(注1)を飲み込みそこなって、むせかえってしまった。ハルナは、心配そうな顔で、ほとんど反射的に彼の背中をさすり始めた。 「あ、せ、せやな、初めてや……」 彼の顔がひどく赤い。ハルナがまだ心配そうに顔をのぞき込んで、「大丈夫?」などと声をかけると、アキオは激しく首を縦に振った。 ふ〜ん……。 「でもさ、大きな花火大会なんて、このあたりじゃ最後かもね」 タイミングを見てあたしが口を挟むと、ハルナの視線があたしに向いて、アキオはちょっと安心した顔になる。貸し一つ、なんて心の中で考えてみたりする。ハルナというと、そんな様子に気づかないようで、ちょっと寂しそうな顔になって、あたしの言葉に小さくうなずいた。 「そうね。もうどこも、花火ってやらなくなってるみたいだし。だからさ、みかげ、今夜は一緒に花火見ない? お父さんも呼んでさ」 「あ、いいよね。せっかくだし、みんなで賑やかに見なくちゃ。アキオも来るでしょ?」 「あ、ああ、ええで」 「じゃぁ、ハルナ、どこで待ち合わせよっか」 「そうね、信号の交差点(注2)あたりかしら。それで思い切ってセンター街(注3)ビルの屋上まで行くなんてどう?」 「あ、それ最高」 センター街と言えば、ポートアイランド方向を見るにはこれ以上の条件はない。あたしは店の裏山の公園(注4)あたりでのんびり見ようかと考えていたが、ハルナの選択のほうが明らかにいい。 それに、やっぱり賑やかなのがいちばん。 「花火は八時からだから、待ち合わせは七時ころかしら」 「えっと……あと一時間もないね」 「そうね。あ、ごめんなさい、わたしちょっと家に寄らないと。じゃぁ」 「あとでね」 ハルナはちょっとすまなそうな表情で小さく手を振る。あたしも軽く手をあげる。ハルナは振り返り、すぐに人混みの中に消えていった。 「そっか、ハルナ、こっちに帰ってきてるんだ」 あたしがそう言うと、アキオは、なにやら気のない返事をしている。ちら、と彼のほうを見ると、やっとソワソワの原因がなくなって安心したのか、ほとんど減っていないイカ焼きをほおばり始めた。 あたしはしばらく、だまってそんなアキオを見ていたがその視線に気づいたのか、アキオはちょっと不機嫌な表情になった。 「な、なにニヤニヤしとう。気色悪いで」 「ん? なんでもないよ〜」 そう言いながら、やっぱりあたしは笑い顔。アキオは余計に憮然とした表情で、横を向いて残ったイカ焼きを平らげた。 「それより、ええんか? あんまりのんびりしとうと、待ち合わせ、間に合わへんで」 「あ、そだよね。店に帰って準備しよっか」 あたしは屋台にはちょっと心残りだったが、せっかくの花火だ、見逃す手はない。あたしたちはそうそうに屋台巡りを切り上げ、坂を下ってバイクのところにもどった。 夏至のころほどではないにしろ、夏の盛りだけあって、午後七時でも外は明るい。店に帰って、このために作ってあったちょっとした食べ物や飲み物をまとめたあたしとアキオは、約束の時間より少し早めにあの交差点に来ていた。 「やぁ、みかげちゃん、早いね」 先に声をかけてきたのは大池先生たちのほうだった。早いね、というわりに、先生のほうが先に来ていたりする。 手には少し重そうな風呂敷包みに、薄手の座布団数枚。もちろん、ハルナも一緒だ。先ほどとは違い、綺麗な浴衣姿。あたしは驚いて、目を丸くした。 「ハルナ、どうしたのその格好」 「どうしたのって、夏祭りはいつもこれよ……、ってそっか、こっちの夏祭りって久しぶりだもんね。それよりみかげこそ、どうしたのそれ」 「あ、うん、去年ね、「みやこ」で買っちゃったんだ」 「いいじゃない。似合ってる」 「えっと、ハルナのほうもすごくいいよ」 彼女の浴衣の色合いはあたしのよりずっとシックだが、なぜか華やかに見える。洋装(しかもひどくセンスがいい)が多い彼女だから、ちょっと新鮮な感じだ。しかもきちんと着こなしている。 そんなとこが、ちょっとだけうらやましかったりする。 あたしの隣では、アキオがなぜか黙ってじっとしている。あたしはそれに気づいて、肘で彼の脇腹をつついてやった。 「ほら、アキオもなんか言いなさいよ」 「あ、うう……」 アキオは目を白黒させながら、小さくあたしをにらみつける。なにか反撃したいらしいが、それを我慢しているのがはっきりわかって、あたしはついニヤニヤしてしまう。アキオはそんなあたしを見て、彼は頬を膨らませて横を向いてしまった。 「あら、アキオ君って昔から無口だもんね。いいんじゃない、無理しなくても」 「あはは、アキオが無口、か、なるほどねぇ」 「え? わたし、何か変なこと言った?」 ハルナはわけがわからない、という表情だ。どっちかと言うと、ハルナの前にいるアキオは無口、なのが正解なのだが、それを言うこともあるまい、ちょっと意地悪の度が過ぎる。もっとも、大池先生もそのあたりがわかっているようで、知らん顔であさってのほうを向いている。 とりあえずあたしたちは、信号の交差点を出てビルに向かうことにした。ここからビルまでは歩いて十五分といったところだろうか。しかし、色々とお喋りをしていると、時間はほとんど感じない。 やがて到着したセンター街。ここは、以前は三宮の商業の中心だった場所だ。三宮の中心ということはすなわち、神戸の中心でもある。そのセンター街も、今は足下に水が来ていて、浅い水面に囲まれている。かつては地下街(注5)もあったのだが、今は魚たちの国だ。 もちろん、そのままではビルに入ることはできない。 あたしたちは、センター街を前にいちど、駅舎跡に入って行く。そこから階段を登ると、そこは物言わぬ改札機。その改札の間を通り、さらに、いくつかあるホームへの上り階段にむかう。ところどころまだ残っている蛍光灯が、その通路をまだら模様に照らしている。 あたしとハルナは、あいかわらず他愛もないおしゃべりをしている。時々大池先生も会話に加わりながら、互いの近況や近頃の神戸の町、「みやこ」の話題で盛り上がっている。アキオは口数は少ないが、スキを見て会話に参加しようとして、うまく乗れずにまた黙っていたりしている。そろそろ彼が少し可愛そうになってきたりするが、下手に助け船を出したりすると逆効果だろうから、あたしは敢えて放っておく。あたりには、あたしたち一行と同じ考えなのか、数人の男女や大人子供が、同じ方向に歩いている。 ホームに出て、少し歩く。その一角には、誰が作ったのか、線路に降りるための木製の階段が据え付けてある。こんなものがあるあたり、やっぱりみんな考えることは一緒なのだろう。それを降り、目の前にもう一つ作られた階段をまた下りると、センター街に渡ることができる、開けた空中歩廊に入れる。こんなふうに、いつのまにか新しいルートが開拓されているあたりが、なんとなくおかしく、同時に、人々の芯の強さを感じさせる。 三宮駅舎跡とセンター街ビルを結ぶ歩道橋。その下、かつて最も混雑した場所の一つだった幅の広い道路は、せいぜいふくらはぎまでとはいえ、既に海になっている。潮の香り。以前、この通り沿いにあった豚まん(注6)屋を思い出して、少しだけしんみりとする。神戸名物、と言うが、中華料理がいつのまにやら名物になっている奇妙さについて、先生と話し合った記憶もある。橋を渡りきると、センタービル街の二階のホール。吹き抜けになった大きな空間はガランとしていて、あたしやほかの人たちの気配だけがその空気に彩りを添えている。階段を探して少し歩き、これから十九階建てのビルの屋上まで歩いて登ることになる。 「いや、この階段はきついね」 大池先生がいかにも疲れたように言うと、ハルナはさもおかしそうに笑った。 「お父さん、運動不足なんじゃないの。ちゃんと散歩してる?」 「おまえなぁ。この年になると高いところに登るのは辛いんだよ」 そんな大池先生はやっぱり途中でバテてしまい、あたしたち三人が背中を押すことになったが、さすがに後半ではあたしたちまで疲れて何度も休みをとることになった。 ようやくビルのてっぺんにたどり着く。もう何人もの人たちが、屋上にゴザを敷いて陣取っている。あたしたちも花火がよく見えそうな場所を選ぶと、そこに座布団を置いて、念のために持ってきた蚊取り線香に火を点け、さっそく持参の食べ物を広げる。大池先生の包みは、卵焼きやら煮物やら、少し手の込んだ料理の詰まった重箱だった。あたしは小さなサンドイッチに生野菜を少し、あぶったソーセージに甘いお菓子を少々といった簡単なものだったから、ちょっと恥ずかしい。 「これ、ハルナが作ったの?」 「そうよ。手抜き料理で悪いんだけど」 「手抜きはあたしのほうだよ。いつこんなの覚えたの」 あたしはつい、箸をとって重箱の中に手を出してしまう。その一つを、ぽい、と口の中に放り込むと、なんだか懐かしい家庭料理の味がして、つい顔をほころばせてしまう。 「みかげぇ、つまみ食いはあかんで」 少し不機嫌そうにアキオが言いながら、アキオは料理の中身に興味津々だ。隅々まで見ているうちに、ふと彼の目が一つの品に留まる。あたしは、それをじっと見つめる彼の視線の先を追ったが、別におかしな品はなかった。つい、変な顔になってしまう。 「あのな、これ、なに?」 彼が指さした先。あたしは少し驚いてしまう。 「あれ、いなり寿司(注7)? どうしたのこれ」 「どう。たまにはいいでしょ?」 「ね、ねぇ、一つ食べていい?」 ハルナの返事を待たずに、あたしは素手でいなり寿司を一つとると、両手で割ってみる。間違いなく本物のいなり寿司だ。しげしげと見てみるが、それはかわらない。 半分にした片方を口に入れてみるが、やっぱり以前から知っているいなり寿司と同じ。 「ハルナ、このお米どこで手に入れたの」 「あのね、「みやこ」に「みちのく」出身の人が留学に来てたのよ。その人の実家のほうだと、まだお米があるんだって」 「そうなんだ。高くなかった?」 「ま、そういうのは言わないのがいちばん」 あたしは、残ったもう片方を口の中に入れ、じっくりと味わった。普段は洋食が多いからお米がないことをあまり意識しないが、こうしてみるとやっぱり、いかに食卓が変化したかを感じてしまう。 「あ、俺も食うわ」 アキオが手を伸ばし、そのいなり寿司を一つとって、そのまま口に放り込んだ。 「ほら、もったいないでしょ、もっと味わわなくちゃ」 あたしがそんなふうに言う様子を、ハルナと大池先生は、やれやれ、といった表情で見ている。 「ねぇ、みかげのもおいしいわよ」 ハルナは、あたしのプチサンドイッチを口に入れている。アキオは慌てて、あたしの用意した食べ物のほうに手を伸ばし、一つつまみ上げるが、まだ口の中に残ったいなり寿司に気づいて、どうしたものかと思案している様子だった。その様子に、あたしはついおかしくなって笑ってしまい、その笑いが他の二人に伝染する。アキオは少し憮然とした表情だったが、口にものが入っている状態では、それも締まらない。 花火まではまだ間があるのに、ちょっと先が思いやられる。もっとも、花火が始まったら食べている余裕なんてなさそうだが。 実際、料理は見ている前で減って行く。でも、なんだか楽しくて手が止まらない。しばらくすると、隣の家族連れの中の十代前半くらいの男の子が、あたしたちの料理に興味津々と言った表情で見ていて、いつのまにか交換会が始まっている。周囲の人まで参加して、おかげで料理のバリエーションはどんどん広がり、重箱やあたしのバスケットの中身は、正体不明なごった煮状態だ。 かたわらで大池先生が、こっそりとお酒を分けてもらおうとしているが、なぜかハルナは即座にそれに気づいて、まるで漫画に出てくる口うるさい母親のような口調で怒っている。ようやくハルナの小言が終わると、先生はこっそりと「実は煙草もなんだ。このところ仙人のような生活でね」などとあたしに耳打ちし、あたしはつい苦笑してしまう。 と、そのときだった。不意に大きな破裂音が、残響を引きながらあたりに響く。アキオは飛び上がるように立って、ポートアイランドのほうを振り返った。 「は、花火、始まってもた」 慌てぶりがおかしい。あたしはつい笑ってしまう。 「これから始まる合図だって。ただの空砲」 「なんや、ひとのことおどかしなや」 アキオがほっと息をつくのがわかる。あたしが、座りなよ、と声をかけると、アキオは南の空から目を離さないように、手探りしながら座布団に腰掛けた。 あたしも座り直して、始まるのを待つことにした。ハルナや大池先生も姿勢を整えるのがわかる。 周囲の人も、いつのまにか、しん、としている。みんなの期待感があたりに満ちる。 しばしの沈黙。この瞬間の気持ちが、なんとなく心地良い。 そして唐突に光の筋が立ち上り、花火が始まった。 大きな花火が夜空を華やかに彩り、ポートアイランドのビルの輪郭を光で描き出す。ぽつりぽつり、という感じ。時々、いくつもの花火が連続して上がると、周囲から歓声がわく。 時々続いたかと思うと、不意に間が空く。緩急つけた打ち上げ方が心憎い。その間に高まる期待感が本当にいいのだ。腕の良い花火職人に違いない。 かつてと比べてずっとおとなしい。むしろ、以前なら花火大会、などという言葉を使うことすらはばかられただろう。でも、花火というものはこんなにも鮮やかで瑞々しいものだっただろうか。昔の記憶をたぐってみても、どうしてもその答えを導き出せない。 昔見た土浦の花火(注8)は、猛烈な勢いで夜空に満ちあふれていた。絶え間ない光の群れに、夜空の黒が隠れてまるで昼間のようだった。まさに光の洪水だった。打ち上げられる花火の数は、今日のような花火大会を何十回でも開けるだろうし、それでもまだ足りないかもしれない。 あの花火も綺麗だった。強烈な思い出なのは確かだ。そのときと比べて、ここの花火はずっと静かなのに、どういうわけかずっと美しく見える。 アキオは、何も言わずに黙って夜空を見上げている。その瞳に飛び散る光が映っているのを見て、あたしはなんとなく微笑んでしまう。アキオはそれに気づく様子もなく、ただ花火に夢中だ。 そしてあたしの気持ちも、いつのまにか花火に向いている。ようやく少し落ち着いてきた周囲のみんなも、時々とりとめもない話をしながらも、やっぱり花火からは目を離そうとしない。 光が踊っている。 こんな印象は初めてだ。どうしていままで、こんなことに気づかなかったのだろう、不思議で仕方がない。なんだか今まで損をしていた気がして、ちょっと胸が締めつけられる思い。 「なんと言うか……いいね、こういうのが」 不意に大池先生が言う。あたしは、それが自分に向けられた言葉だと気づいて、ただ、うん、とだけ答える。 花火は半時あまりも続いただろうか。最後に大きな花火が上がると、お開きになった。そのころにはあたしたちは、光の宴にすっかり酔っていた。 しばらく動きたくなかった。みんな、何かとりとめのない言葉や花火の感想、思い出などをぽつり、ぽつりと話ながら、静かになった夜空を見上げていた。あたしたちが余韻を楽しみながら動き出したのは、それから小一時間ほども経ってからだった。 ゆっくりと時間をかけて信号の交差点に着いて、そこから分かれるまで、あたしたちは口少なだったが、それで充分だった。 夏祭りはいつものことだったが、この年の祭りは特に強烈な思い出として記憶に残ることになったし、それはアキオも同じようだった。今年の夏祭りは、そんな思いと共に終わりを告げた。 そして、夏祭りにはちゃんと後日談がある。それは、あの花火からひと月ほど経ったある日だった。 この間、神戸の町は少し静かになる。暑くて誰も仕事にならない、というのも確かにあるが、お盆の時期を楽しみたいという、みんなの共通した思いに違いない。 華やかな記憶が落ち着いた思い出に変わりつつあったその日、あたしは夏祭りの最後の仕上げをする。 と言っても、その日はほとんど何もせず、店も閉め、裏山の展望台の木陰に食べ物や飲み物、本やラジオを引っ張り出して、ベータも連れ出し、ただ日がな一日のんびりするだけだ。そばには、そこの雰囲気にちょっとだけ不釣り合いな、線香立てと火のついた線香。毎年の行事。仕事も何もかも忘れて心の洗濯をする時間。 そのことをアキオもわかっていて、黙って草むらに足を放り出しているだけだ。ときどき、どちらかがラジオのトーク番組の内容に口を挟むくらい。仔猫たちに尻尾にじゃれつかれたベータは、さも鬱陶しそうに尻尾を動かすが、二匹はそれがよけいに楽しいらしく、一段と激しく暴れ回る。あたしとアキオは、それがおかしくてつい、吹き出す。 真っ青な空と、群青色の海と、深い緑色の木々。それらの中から生えたビルたちも、かすかな霞の向こうながら、どこか鮮やかな色をしている。 ただ何もなく、淡々とした時間を過ごす。暑さは身にしみるが、騒々しい蝉の声を聞いていると、その暑さも風流に感じるから不思議だ。やがて日が傾き始め、浜風(注9)が止むころに、あたしとアキオはやっと動き出す。どちらが言うまでもなく、のんびりと後片づけをして、まるで最初から何事もなかったかのように綺麗にしてしまう。 さっぱりした状態で部屋に入り、水筒に水を汲む。そして、一日中焚いておいた線香をとった。 「さ、行こうか」 「そやな」 それだけ言うと、あたしたちは家を出た。 のんびりと歩いて坂を下る。斜めに射す日の光はまだ暑くて、あたしたちは日陰を選んで歩いてしまう。いつものようにとりとめのないお喋り。その合間にちょっとじゃれあうが、今日はそのどちらも少し静かだ。 少しずつ日が傾く中、そうやって歩く。会話は最初はあの祭りや花火の話が多かったが、いつのまにか先生の思い出が中心になってしまう。どちらかというと先生を崇拝気味のアキオは、あたしが先生の失敗談や子供みたいな癖を話してやると、いちいち驚いた表情をするのだった。 小半時以上もかけて、普通ならバイクを使うような距離を、山を右手に見ながらゆっくりゆっくりと歩く。少しずつ山風が吹き始め。涼しくなりつつある。 やがてあたしたちは、道の右手の急斜面を斜めに登る狭い坂道に入る。いつも坂を歩いているとはいえ、この道は少し重労働だ。何度も折り返す坂道を、息を切らしながら登りきる。 「わ、やっぱりすごい眺めだ」 坂の終点の広場で、あたしはついそう言ってしまう。すぐ後から登ってきたアキオも、 「ほんまやなぁ」 と、しみじみした声で言う。 もちろん、標高だけで言えば、ここは店のあたりよりもずっと低い。でもそれゆえに、神戸の街並みが近く感じられる。それが独特の雰囲気。毎年ここに来ているのに、つい見とれてしまう。 なによりここは、ポートタワーが近い。木々や無人のビルのちょっと向こうに、独特のフォルムをしたタワーが、すぐむこうで海を背景にして立ちつくしているのだ。それが、自分が神戸にいることを改めて実感させてくれる。 「ほんま先生も、ええとこ選んだわ」 「そだよね」 言いながらあたしは、本来の目的を思い出して、その風景を背に振り返った。 そこにあるのは、たち並ぶ数々の墓石。 その多くは少し古びている。少し伸びた草が周囲を包み、伝統的な墓地の雰囲気とは少し違うが、背景の山の緑色を背にしていると、なんとなくこれはこれでいい気もしてくる。 あたしはその一つに近づく。数日前に既に草は刈ってあるから、今日は水をかけてやるだけだ。本当なら柄杓に桶と行きたいところだが、さすがにその備えはないから、諦めるしかない。 そして墓石の前に線香を立て、小さく手を合わせる。 「なぁ、みかげ」 「ん?」 「これ、送り火、いうヤツやろ?」 「なぁに、いまごろ」 「なんでもない」 変なことを言うアキオに、あたしはちょっと苦笑して見せる。アキオはそんなあたしに気づいたのか気づかなかったのか、墓石に向かって、あたしと同様に手を合わせていた。 しばし、そうしている。あたしは充分にその雰囲気に浸ってから、ようやく立ち上がった。 「さ、帰ろ。夏の行事もこれで全部終わり」 「あぁ、明日からまた仕事や。なんやダルいわ」 「ほらほら、こんなことで、いちいちだらけない」 あたしが軽くアキオの頭を叩いてやると、アキオはわざと怒った顔をしてみせる。 「は、叩かんでもええやんか」 「アキオの頭、このくらい刺激があったほうが良くなるんじゃない?」 「なんやて」 アキオがふざけて上げた手を、あたしは大げさに避けてみせる。あたしが笑いながら駆け出すと、ふくれっ面のアキオが追いかけてきた。 そのままあたしたちは、騒がしい笑い声とともに坂を駆け下りていった。いつものあたしたちと全くかわりもなく。 澄んだヒグラシの声と、線香のほのかな香りだけをその場に残して。 |
  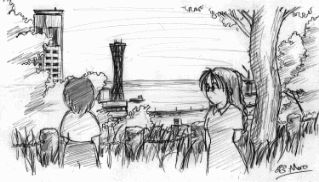 |
|
注1 イカ焼き: あたりまえだけど、出てくるイカ焼き、イカを卵でとじて鉄板で焼いたほうっす。イカの姿焼きを想像しないでください。<< 注2 信号の交差点: Episode II参照。<< 注3 センター街: 三宮駅の南にあるビル。デパートというより、高層化された巨大な商店街といった感じ。隣の元町駅の近くまで続いており、三宮駅地下街(さんちか)と複合して、一大繁華街となっている。神戸の商業の中心地。<< 注4 裏山の公園: たぶん、すぐにはわからないと思うけど、みかげの家の裏手には展望台があるんす。いまでもあります。わかる人にはわかると思うけど。確かにポートアイランドで上がる花火を見るには少し遠いっす。<< 注5 地下街: サンチカのこと。専門的な店も多い地下商店街で、センター街と一体となって神戸の「お洒落な」側面の一翼を担っている。<< 注6 豚まん: 言わずと知れた神戸名物。ようは、豚肉入りの中華まんじゅう。物語に登場したのはサンプラザにある豚まん屋で、ここのは間違いなく逸品。是非ともいちど試して欲しい。<< 注7 いなり寿司: 関西以外の人のために念のため。関西のいなり寿司は基本的に三角形をしている。地方によっては俵型だが、関東のいなり寿司と比べると大きい。また、中身は野菜の混ざった混ぜ御飯風。子供の拳くらいあって、一口で食べるのは無理。<< 注8 土浦の花火: 霞ヶ浦で開かれる花火大会のこと。正確には、いわゆる夏場の花火大会ではなく、秋口に行われる花火の品評会のようなもので、最新の花火が派手に、しかも猛烈に上がる。<< 注9 浜風: 日中、浜から山に向かって吹き上げる風のこと。気象学的には「谷風」というのが正しいが、神戸では「浜風」と呼ばれる。それに対し、夜間には山のほうから風が吹き、これを「山風」と言う。朝と夕方には風が止み、これが「朝凪」と「夕凪」。神戸のように山が海に近づいている場所に住む人たちは、こうした風で時間を感じる。<< |