 Prologue 藤代書店
Prologue 藤代書店Prologue 藤代書店
|
どてっ。 「ぎゃっ!」 左の腰をしたたか打ちつけて、あたしは目覚をさました。寝ぼけた頭で、ああ、またベットから落ちたんだな、と考える。 落ちるたびに毎回、ぶつける場所が違うが、左側をぶつけたのは久しぶりだ。それにしても、高さが二十センチはある手すりを乗り越えて転落するんだから、我ながらまったく器用なことだと思う。 「あ〜、いたたた……」 思わず言葉が漏れる。もちろん、言ったところで痛みが和らぐわけではない。 とりあえず左手で腰をさすりながらなんとか起きあがると、視界の中にほんのり白い明かりが見えて、窓の外から明るい光が射しているのが頬にも感じられる。どうやらもう、かなりいい時間になっているらしい。あたしはあたりを手探りしながら、なんとかまたもとのベットに這い上った。 「眼鏡、眼鏡……」 古いマンガの一シーンのようなことを言いながら、枕元に設えてあるはずの眼鏡入れを手探る。知らない人が見れば冗談ぽく見えるかも知れないが、とにかく本当に見えないのだ。 そして、あたしの朝は、この行事でいつも、ほぼ三分は無駄になる。 とにかくひどく寝相の悪いあたしが眼鏡をなくしてしまわないよう、先生はわざわざ、眼鏡入れを壁から下げるようにしてくれたのだが、あたしはと言えば、その眼鏡入れすら自力で発見できず、ひどく手探りしてしまう。先生が「しなのの国」まで行って特注してくれた、超高屈折率ガラスを使った眼鏡をようやくみつけ出し、起き抜けのおぼつかない手でかけると、色だけだったスーラ調の世界が突如として、鮮明な現実世界となって、あたしの前に開けた。 大きくため息をつき、ベットの上に座り直して、枕元の時計をのぞき込む。 「あ〜……八時四十六分、と」 目覚ましも兼ねて、声を出して読み上げる。けして早い時間ではないが、今日みたいに、ただ店を開ければいいだけの日なら、起きるにはさほど遅すぎるとは言えない時間だ。 正直言って、まだ眠い。けれど、いつまでもゆっくりはしていられないのも確か。あたしは目を覚ますために軽く体を動かすと、自分に勢いをつけるために三つ数え、一気にベットから飛び出した。 朝の開店準備と言うとちょっと大げさに聞こえるかもしれないが、うちは小さな古書店、別にたいしたことはしない。せいぜい、あたし自身が着替えと食事を済ませたら、前日の埃をハタキで一通り落とし、あとは扉の鍵を開いて「Closed」の札を「Open」に裏返すだけ。全部をゆっくりやっても、今から開店時間に十二分に間に合ってしまう。 だからあたしは、まったくいつもの通りにラジオのスイッチを点けると、食料棚から野菜を少々と、ハムにチーズ、最近は少々高価になってきたパンなどを取り出し、手早く洋風な朝食を作る。タイミングを見て濃いめの紅茶を準備するのも忘れてはいけない。ここしばらく卵を切らしているから、大好きな(実を言うと、あたしが、というより先生が、だが)スクランブルエッグは作れない。 そろそろ買い出しに行きたいが、なんだかつい、億劫になってしまう。これも一人暮らしになってダレてしまったせいかもしれない。 そう言えば、胡椒も切れかけている。使い続けたら数日も保たないだろう。 「今度の定休日、まちまで買い出しかな」 大きめの声で独り言。誰も聞いていないことがわかっていて、つい独り言が出るのは、自分が孤独な証拠だと、先生が言っていたのを思い出す。そんな先生もむやみに独り言が多かった気がするが、はたして先生は孤独だったのだろうか。あたしはそんなことは想像したくない。あたしの独り言は、そんな先生の癖が移っただけなのだと、そう思いたいが、実際はどうなのだろうか。 そう言えば、あたしの名前が「藤代みかげ」だからよく間違える人がいるが、店の名前の「藤代書店」はもともと、先生の名字が由来だ。色々あってあたしは、神戸に来てから藤代姓を名乗っているが、正直言ってこの習慣にはいまだに慣れていない。そのせいかあたしは、今でもこの店を自分の店という事実に、今ひとつ実感がない。 現実にはそんなことはないとわかっていながら、今でも店は先生のもの、っていうイメージが残っている。 そんな、ちょっとした物思い。あたしは作った朝食を、台所と一続きの居間のローテーブルに置き、毛足の長い絨毯の上のクッションに座って、のんびりと片づけてやる。先ほどから部屋の空気を満たしているラジオの音といえば、最近は音楽番組やドラマが増えた気がする。実際にいまも、なんだかなつかしい洋楽の明るい歌が流れている。 ……幸せなことはないの? 歌を聴くときみたいに…… 聞いたことのある曲。曲名は知らないが、そんなことは気にならない。甘い曲はしばらく続き、やがてそれが終わると不意にニュースが始まる。内容はと言うと、当てにならない天気予報や農業情報、最近開通した道や、それ以上に多い、幹線道路の閉鎖情報など。のんきなニュースはすぐ終わり、始まったトーク番組は、妙に地元の話題が多い。 以前は少し馴染めなかったそんな雰囲気も、今は少し好きになってきている。 簡単な朝食は、準備からぜんぶ済ませるまで二十分もかからない。食器をかたづけ、一息ついてから、箒とハタキを手に、薄暗い店の方に入る。 まずは窓を開け、店に光を招き入れる。と言っても、本にはむやみに日光は当てられないから、開ける窓も限られるが、そんな光でさえ、店の奥に届けばこの部屋全体が目覚めたように感じる。 ハタキのほうで昨日の埃を軽く落とし、今度は扉を開けて通りに顔を出す。そろそろ高くなった春の日差しに、視界が一瞬、真っ白になる。手のひらをかざして空を見上げると、久々に抜けるような青空だ。普段の空は青い絵の具を流したように見えるが、今日みたいな日に空を見上げると、そんな形容は浮かんでこない。そもそも世界は青いほうが正しくて、あたしたちの立っている地面のほうが色を間違えているんじゃないか、そんな感じだ。 「そろそろ少し、畑のほう、見てこなくちゃなぁ」 またもや独り言。そのままあたしの視線は、高く見上げた空から、独りでに店の正面、海の見える南の方へと降りて行く。 浜からかなり登った急斜面に位置し、深い森を背負ったこの高台も、人の住む家はまばらになり、この店の周りも数軒の家が見えるだけ、あとは草に覆われた空き地だ。あたしの眼下は急な斜面で、店の前からですら一気に数十メートルも下っている。その斜面を、まっすぐに道が下る。舗装はもうボロボロで、ほとんど砂利道と言ってもいいくらいだ。 斜面の下は不意に、広く緩やかなスロープになっている。そこから広がる灌木と人の背より高い草の緑色の間には、日差しを浴びて白く輝くアスファルトと、取り壊されることすら忘れてしまった家々の直線的な輪郭が、ふと思い出したように残って平坦な風景に変化をつけている。そのスロープをかなり下った先、木々のとぎれた先には、びっしりと蔦に覆われた、四角く大きな駅舎跡。そこから奥には、かつて浜手の街並みや人工島のあった、浅い水面からにょきにょきと生えるビルの群れ。長いリボンがからみつくように水上に浮かぶ昔の高架道路。ひときわ目立つ、赤く大きなアーチ橋。 右手に見えるのは、やはり水中から生えた、あたしたちの町「神戸」のシンボル、ポートタワー(注1)。赤い色は、以前よりくすんできたと聞いているが、あたしの目にはまだまぶしい。 見慣れた風景。神戸の街が一望できる。先生がこの店を気に入った理由がこれだった。朝起き、こうして通りに出るたびに、いつも見ているのに、それでもつい、こうやって見入ってしまう。 それは、お祭りのようだった、かつての世の中の名残り。すっかり静かになった今の世の、明け方に見る夢のような思い出。 海と森に優しく包まれ、静かに眠る、色とりどりの記憶たち。 誰かが、今は黄昏の時なんだ、と言っていた。誰だったろう、思い出せない。あたしはもうちょっと違う気もしているが、でも、その言葉にはなんだか不思議な響きがあって、最近はなんだかそれもいい気がしている。 そしてあたしたちロボットは、そんな黄昏をじっと見て行くのだとも。 そんな物思いに二、三分もふけっていたのだろうか。あたしはまた、大きく息をした。 「さぁて、今日も一仕事しよ」 声に出してそう言う。また一日の始まりだ。今日はどんな日になるのだろうか。 |
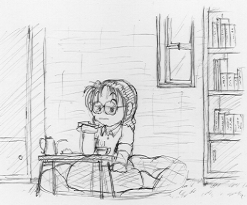  |
|
注1 ポートタワー:神戸のメリケン広場に作られたタワー。鼓のような形が特徴的。現在は山手の街路から見ることはかなり困難だが、この物語では建物が少なくなっており、ポートタワーまで見通せるとした。<< |